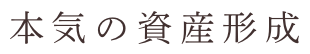「なぜかいつもお金がない」「気づいたらお金を使いすぎている」と悩んでいませんか。
その原因は、単なる無駄遣いではなく、ストレスや見栄といった心理的な要因や、お金の管理方法にあるのかもしれません。
この記事では、お金を使いすぎる人の心理や共通する7つの特徴を徹底解説します。さらに、浪費癖を根本から治すための具体的な対策も紹介。
お金を使いすぎる問題は、まず自分の収支と向き合い、お金の使い方に明確なルールを設けることで改善できます。
本記事を参考に、無駄遣いを卒業し、賢くお金と付き合う方法を身につけましょう。
なぜかお金を使いすぎる…その背景にある心理的な原因とは
「今月もなぜかお金がない…」「給料日直後なのに、もうお財布が寂しい」と感じていませんか?計画的にお金を使っているつもりでも、気づけば予算オーバー。その原因は、単なる「無駄遣い」や「計画性のなさ」だけではないかもしれません。実は、お金を使いすぎてしまう行動の裏には、私たちの心が深く関係していることがあります。
ここでは、浪費の引き金となる3つの心理的な原因を詳しく解説します。
ストレス発散や自分への甘え
仕事のプレッシャーや人間関係の悩みなど、現代社会はストレスの連続です。こうしたストレスが溜まったとき、そのはけ口として買い物に走ってしまう人は少なくありません。「頑張った自分へのご褒美」という名目で欲しかった服を買ったり、少し高価なスイーツを食べたりすることで、一時的に気分が高揚し、嫌なことを忘れられます。これは、ストレスを感じたときに、手っ取り早く快感を得るための手段として買い物を選んでしまっている状態です。しかし、この方法で得られる満足感は長続きせず、根本的なストレス解決にはなりません。むしろ、後から「また無駄遣いしてしまった」という罪悪感に苛まれ、新たなストレスを生む悪循環に陥りがちです。
見栄や承認欲求を満たしたいサイン
「周りからすごいと思われたい」「リッチな生活を送っているように見られたい」といった見栄や承認欲求も、浪費の大きな原因となります。特にInstagramなどのSNSで、友人やインフルエンサーの華やかな投稿を目にする機会が増えた現代では、他人と比較して自分も同じように見せたいという気持ちが働きがちです。他人からの評価を過度に気にし、自分の価値を「持っているモノ」や「している体験」で証明しようとしてしまうのです。ブランド品や流行のファッション、話題のレストランでの食事などにお金を使うことで一時的に欲求は満たされますが、それは本当の自分を豊かにするものではありません。むしろ、他人に見せるための出費を続けることで、経済的に追い詰められてしまう危険性があります。
自己肯定感の低さを買い物で埋めている
自分に自信が持てなかったり、何かしらのコンプレックスを抱えていたりすると、その心の隙間をモノで埋めようとすることがあります。新しい服やコスメ、高価なアクセサリーなどを手に入れることで、一時的に「理想の自分」に近づけたような感覚になり、自信が湧いてくるように感じられるのです。これは、買い物という行為を通して、一時的に自分の価値を高め、心の空白を埋めようとしている心理状態と言えます。しかし、モノによって得られる自信は非常に脆く、すぐに色褪せてしまいます。そのため、その感覚を維持しようと次から次へと新しいものを求め、結果として浪費が止まらなくなってしまうのです。根本的な自己肯定感の低さと向き合わない限り、買い物への依存から抜け出すことは難しいでしょう。
お金を使いすぎる人に共通する7つの特徴を紹介
あなたはお金を使いすぎていると感じていませんか?浪費癖のある人には、実はいくつかの共通した行動パターンや考え方の特徴が見られます。ここでは、お金を使いすぎる人に共通する7つの特徴を具体的に解説します。自分がいくつ当てはまるか、チェックしながら読み進めてみてください。
①:新商品や限定という言葉に弱い
「期間限定」「数量限定」「新発売」といった言葉に心を動かされ、つい財布の紐が緩んでしまうのは、お金を使いすぎる人の典型的な特徴です。本当に必要かどうかを冷静に考える前に、「今しか手に入らない」という希少性や特別感に価値を感じてしまい、購入すること自体が目的になっています。「これを逃したら損をする」という焦りから、本来は不要なものまで買ってしまうのです。
②:セールでつい不要なものまで買って後悔する
セールや割引キャンペーンは賢く利用すれば節約につながりますが、浪費癖のある人にとっては逆効果になることがあります。「70%OFF」といった割引率の高さに興奮し、「お得に買えた」という満足感を得るために、使う予定のないものまで買ってしまうのです。家に帰ってから「どうしてこんなものを買ってしまったんだろう」と後悔するものの、また次のセールで同じことを繰り返してしまいがちです。
③:クレジットカードを積極的に使ってしまう
クレジットカードは、現金がなくても買い物ができる便利なツールですが、その手軽さが浪費を助長する一因となります。お金を使いすぎる人は、手元の現金が減らないため、お金を使っているという感覚が麻痺しやすい傾向にあります。ポイントが貯まるからという理由で何でもカードで支払ったり、安易にリボ払いや分割払いを利用したりして、気づいたときには請求額が膨れ上がっているというケースも少なくありません。
④:自分の収入と支出を正確に把握していない
浪費癖を治す上で最も根本的な問題ともいえるのが、家計管理の欠如です。自分の毎月の手取り収入がいくらで、何にどれくらいのお金を使っているのかを全く把握していない、いわゆる「どんぶり勘定」の状態です。家計の現状が分かっていないため、自分の経済状況に見合わないお金の使い方をしても危機感がなく、使いすぎにブレーキがかかりません。「給料日前はいつもカツカツ」という人は、この特徴に当てはまる可能性が高いでしょう。
⑤:コンビニに立ち寄るのが癖になっている
特に買うものがなくても、通勤途中や帰り道にコンビニに立ち寄るのが習慣になっていませんか?コンビニには新商品のスイーツやドリンク、雑誌など魅力的な商品が並んでおり、「ついで買い」を誘発します。1回あたりは数百円の少額な出費でも、毎日続ければ1ヶ月で数万円の大きな浪費につながります。目的のない立ち寄りは、無駄遣いの入り口となっているのです。
⑥:趣味や推し活にお金をかけ過ぎている
趣味や好きなアイドル・キャラクターを応援する「推し活」は、日々の生活に彩りを与えてくれます。しかし、そこに注ぐ情熱が強すぎるあまり、お金を使いすぎてしまう人もいます。「推しのためなら」「自分の唯一の楽しみだから」という気持ちが、生活費との境界線を曖昧にし、冷静な金銭感覚を失わせることがあります。限定グッズやイベント、遠征費用などが際限なくかさみ、気づけば生活を圧迫するほどの支出になっていることも珍しくありません。
⑦:具体的な貯金の目標や計画がない
「いつかお金を貯めたい」と漠然と思ってはいるものの、具体的な目標や計画がないため、手元にお金があるとつい使ってしまうのも特徴の一つです。「1年後に海外旅行へ行くために50万円貯める」といった明確なゴールがないと、日々の節約に対するモチベーションが続かず、目先の欲求を優先してしまいます。その結果、お金を「残す」ことよりも「使う」ことが習慣になってしまうのです。
もしかして病気?お金の使いすぎと関連する精神的な疾患
「自分の意思ではどうしてもお金の使いすぎがやめられない…」もしあなたがそう感じているなら、それは単なる浪費癖ではなく、背景に精神的な疾患が隠れている可能性も考えられます。もちろん、お金を使いすぎてしまう全ての人が病気というわけではありません。しかし、特定の疾患の症状として、浪費や衝動買いが現れることがあるのも事実です。
ここでは、お金の使いすぎと関連が指摘される代表的な精神疾患を3つご紹介します。ご自身の状況を客観的に見つめるきっかけとして、参考にしてみてください。
衝動が抑えられない買い物依存症
買い物依存症(買い物嗜癖)とは、買うという行為そのものへの依存によって、自分でもコントロールできないほど買い物を繰り返してしまう状態を指します。欲しいものを手に入れるためではなく、「買う」という行為自体が目的となり、その瞬間の高揚感や満足感を得るために買い物をやめられなくなります。ストレスや孤独感を埋めるために買い物を繰り返し、購入後には強い罪悪感や自己嫌悪に陥るという悪循環にはまりやすいのが特徴です。借金をしてまで買い物を続け、結果的に人間関係や社会生活に深刻な支障をきたすケースも少なくありません。
ADHD(注意欠如・多動症)の特性による衝動買い
ADHD(注意欠如・多動症)は、不注意・多動性・衝動性といった特性を持つ発達障害の一つです。このうち「衝動性」の特性が、お金の使いすぎに直結することがあります。欲しいと思った瞬間に「後で支払いに困るかもしれない」という結果を予測するよりも、目の前の欲求を優先してしまう傾向があるためです。また、「不注意」の特性から、自分の収入や支出を正確に管理するのが苦手で、気づいた時にはお金がなくなっているという事態に陥りがちです。ADHDは本人の性格や努力不足の問題ではなく、生まれ持った脳機能の特性であることを理解することが重要です。適切な対策や治療によって、衝動的な行動をコントロールしやすくなります。
双極性障害の躁状態による浪費
双極性障害は、気分が異常に高揚する「躁状態」と、意欲が低下し気分が落ち込む「うつ状態」を繰り返す病気です。特にお金の使いすぎが問題となるのが、この「躁状態」の時期です。躁状態になると、自分は万能だと感じ、眠らなくても平気になったり、次々とアイデアが湧いてきたりします。この高揚した気分から判断力が低下し、気が大きくなることで、普段なら手を出さないような高額な商品を次々と購入してしまうことがあります。本人はそれを「良い買い物」だと信じているため、周囲が止めても聞き入れません。しかし、その後うつ状態に移行すると、浪費してしまったことへの激しい後悔と罪悪感に苛まれることになります。
徹底解説!お金を使いすぎる浪費癖を治す具体的な5つの対策
お金を使いすぎてしまう癖は、決して治せないものではありません。原因を理解し、正しい対策を一つずつ実践していくことで、誰でも着実に改善できます。ここでは、浪費癖を克服し、健全な家計を取り戻すための具体的な5つの対策を徹底解説します。
①:現状把握が第一歩 家計簿アプリで収支を可視化する
浪費癖を治すための最初のステップは、自分のお金の流れを正確に把握することです。「何に」「いくら」使っているのかを知らないままでは、改善のしようがありません。そこでおすすめなのが、スマートフォンで手軽に管理できる家計簿アプリの活用です。
「マネーフォワード ME」や「Zaim」といったアプリは、銀行口座やクレジットカードと連携させることで、収入と支出を自動で記録・分類してくれるため、手間なくお金の動きを可視化できます。まずは1ヶ月間、すべての支出を記録してみましょう。思った以上にお金を使っている項目(例えばコンビニやカフェ代など)が見つかり、意識改革のきっかけになるはずです。
②:お金の使い方にルールを作る
感情に流されてお金を使ってしまうのを防ぐには、自分だけの「お金のルール」を設定することが非常に効果的です。意志の力だけに頼るのではなく、支出をコントロールする「仕組み」を作りましょう。今日から始められる具体的なルール例をいくつかご紹介します。
- 給料日に「先取り貯金」をする:給料が振り込まれたら、まず貯金分を別の口座に移します。財形貯蓄や自動積立定期預金などを利用するのも良い方法です。
- 1ヶ月に使えるお金を決める:収入から貯金額と固定費を引いた残りを「今月使えるお金」とし、その範囲内で生活することを徹底します。
- クレジットカードの利用を制限する:普段の買い物は現金やデビットカード、スマホ決済のチャージ残高など、手持ちの範囲で支払うようにし、クレジットカードは家賃や光熱費などの固定費決済専用にしましょう。
- 高額な買い物は即決しない:「1万円以上のものを買うときは、1週間考える」といった冷却期間を設けることで、衝動買いを大幅に減らせます。
大切なのは、自分にとって無理なく続けられるルールを見つけることです。まずは一つでも良いので、実践してみましょう。
③:衝動買いを防ぐ対処法を身につける
「限定品」「セール」「残りわずか」といった言葉に弱く、つい衝動買いをしてしまう方は、意識的な対策が必要です。衝動的な購買意欲が湧いたときに、それを乗り切るためのテクニックを身につけましょう。
まず、「欲しい」と感じたらその場ですぐに買わず、一度スマートフォンのメモ帳などに「ほしい物リスト」として記録します。そして、「それは本当に今すぐ必要なのか?」「他のもので代用できないか?」「1ヶ月後も本当に欲しいと思うか?」と自問自答する癖をつけましょう。多くの場合、時間をおくことで冷静になり、購買意欲が薄れていきます。また、空腹時や疲れているときは判断力が鈍りやすいため、そういった状態での買い物を避けることも有効な対策です。
④:お金のかからないストレス解消法を見つける
買い物がストレス発散の手段になっている場合、浪費癖を根本から治すのは困難です。お金を使うこと以外で、心を満たせる趣味やストレス解消法を見つけることが重要になります。
お金をかけずにリフレッシュできる方法はたくさんあります。例えば、近所の公園を散歩する、YouTubeで好きな音楽を聴きながらストレッチをする、図書館で本を借りて読む、お風呂にゆっくり浸かる、信頼できる友人と電話で話すなどです。自分に合ったストレス解消法を複数リストアップしておき、ストレスを感じたらすぐに実行できるように準備しておくと、買い物への依存から抜け出しやすくなります。
⑤:明確な貯金目標を立てる
ただ漠然と「節約しなきゃ」「貯金しなきゃ」と考えているだけでは、モチベーションは長続きしません。なぜお金を貯めたいのか、その先の具体的な目標を設定することで、日々の節約が「我慢」から「未来への投資」へと変わります。
「1年後に50万円貯めて、憧れの沖縄旅行に行く」「3年後に200万円を貯めて、引っ越しの初期費用にする」など、「いつまでに」「いくら貯めて」「何に使うのか」を具体的に設定しましょう。目標が具体的であるほど、達成したときの自分の姿を想像しやすくなり、モチベーションが維持しやすくなります。目標を紙に書いて部屋に貼ったり、スマートフォンの待ち受け画面に設定したりして、常に意識できるようにするのもおすすめです。
もっと詳しく知りたい方は、「毎月の出費を抑える10のコツ」をご覧ください。
お金のプロから教わるという解決方法もアリ!
ここまでご紹介した対策を実践しても、
「自分一人ではどうしても浪費癖が治らない」
「何から手をつければ良いのか分からない」
と悩んでしまう方もいるかもしれません。
そんな時は、一人で抱え込まずにお金の専門家の力を借りるという選択肢も非常に有効です。
ファイナンシャルプランナー(FP)のようなプロは、客観的かつ専門的な視点から、あなたに合った改善プランを提案してくれます。
自分では気づけなかったお金の使い方や問題点を指摘してもらうことで、浪費癖の根本的な原因にアプローチしやすくなります。
ここでは、具体的なサービスの一例として、お金のトレーニングサービスをご紹介します。
ABcash|お金のプロによるオンライントレーニング
「ABcash(エービーキャッシュ)」は、お金のプロである専属コンサルタントが、オンラインでマンツーマンのトレーニングを行ってくれるサービス。
単なる家計簿のつけ方だけでなく、お金を使いすぎる根本的な原因の分析から、将来を見据えた資産形成まで、体系的にサポートしてくれます。
お金のプロがマンツーマンで伴走してくれるため、途中で挫折しにくく、一生役立つお金の知識と習慣が身につくことが期待できます。
何から始めていいかわからない方や、これまで何度も家計管理に失敗してきた方にとって、心強い味方となるでしょう。
まとめ
本記事では、お金を使いすぎる人の心理的な原因や共通する特徴、そして浪費癖を治すための具体的な対策を解説しました。
お金を使いすぎてしまうのは、単なる癖ではなく、ストレスや見栄、自己肯定感の低さといった心理が深く関係している場合があります。
浪費癖を改善するためには、まず家計簿アプリなどで収支を「見える化」し、自分のお金の使い方を客観的に把握することが不可欠。その上で、お金を使うルールを設けたり、衝動買いを防ぐ工夫をしたりすることで、無駄遣いは着実に減らせます。
一人で抱え込まず、この記事で紹介した対策を実践し、計画的なお金の管理を目指しましょう。