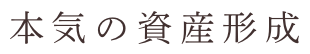本ページはプロモーションが含まれます。
「毎月の出費をできるだけ抑えたい!!」
こう考える方も多くいるでしょう。
FPという職業柄、「ムダ遣いを抑えるには?」というご相談をよくいただくので、
「毎月の出費を抑えるコツ10個」と
「無理なく続ける3つの秘訣」を
この記事で解説していきます。
- 収入より出費が多くて貯金できない人
- 面倒くさがりのため三日坊主で終わってしまう人
私もこの方法を利用して、出費を抑えることで運用にまわす余剰資金ができました。
どれも比較的簡単な方法なので、最後までぜひチェックしてみてください。

この記事では、毎月の出費を抑えるコツを10個厳選して紹介します。
保険料などの固定費と、日々の食費といった変動費の両面からアプローチ。
また、挫折しないための継続する秘訣も解説します。
なぜ今出費を抑える必要があるのか
- 「毎月の支払いが厳しい」
- 「もう少し貯金に回したい」
- 「一人暮らしを始めたばかりで生活費が心配」
と感じている人は少なくないでしょう。
ここでは、なぜ今、出費を抑える必要があるのか、その具体的な理由を3つ解説します。
物価上昇と実質賃金の低下が家計を直撃
ニュースで「物価高」という言葉を耳にしない日はありません。
食料品やエネルギー価格をはじめ、身の回りのあらゆるモノやサービスの値段が上昇を続けています。
一方で、給与の上がり幅は物価の上昇ペースに追いついていないのが現状。
つまり、以前と同じ生活を続けているだけで、気づかぬうちにお金が減っていくという状況です。
| 品目 | 概要 |
|---|---|
| 食料品 | 生鮮食品から加工食品、外食に至るまで、幅広い品目で価格が上昇。家計の基本となる食費への影響は大きい。 |
| 光熱・水道費 | 電気代や都市ガス代など、エネルギー価格の高騰が直接的に反映され、毎月の固定費を押し上げている。 |
| 日用品 | トイレットペーパーや洗剤といった生活必需品も、原材料価格の上昇などを理由に値上がりが続いている。 |
参考リンク:
– [消費者物価指数(CPI) – 総務省](https://www.stat.go.jp/data/cpi/index.html)
– [毎月勤労統計調査 – 厚生労働省](https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html)
将来の「もしも」に備える資金の重要性を解説
人生には、結婚や出産、住宅購入といった大きなライフイベントが待ち受けています。
また、病気やケガ、突然の失業など、予測不可能な事態が起こる可能性も。こうした「もしも」の時に頼りになるのが、日々の貯蓄です。
特に、老後の生活資金については「老後2000万円問題」が話題になったように、公的年金だけではゆとりある生活を送るのが難しい時代になりつつあります。
将来の不安を軽減し、安心して生活するためには計画的な資産形成が不可欠。その第一歩が出費の見直しなのです。
「節約」は我慢ではなく「豊かな生活」への投資
出費を抑えることに対して、「我慢」「切り詰める」といったネガティブなイメージを持つ人もいるかもしれません。
しかし、家計を見直し、無駄な支出を特定して抑えることは、自分の価値観を見つめ直し、お金の使い方にメリハリをつけることに他なりません。
無駄を減らすことで生まれたお金や時間は、貯蓄や投資に回すだけでなく、自己投資や趣味、大切な人との時間など、自身の人生をより豊かにするために使うことが可能。とくに、節約術を活用することで、日々の生活費を効率的に管理し、将来のための資金計画を立てることができます。
節約は、未来の自分への「投資」と捉えることが重要であり、節約生活を楽しむことで、より豊かなライフスタイルを実現することができるでしょう。
節約術のポイントは無駄な出費の洗い出し

毎月の出費を効果的に抑えるためには、まず自分が「何に」「いくら」使っているのかを正確に把握しましょう。
支出を「見える化」し、客観的なデータに基づいて改善点を見つけ出すことが、無理なく節約を成功させるための最初のステップです。
家計簿アプリで支出を管理する
支出を把握する最も手軽で効果的な方法が、家計簿アプリの活用です。
手書きの家計簿と異なり、アプリは金融機関との連携機能が充実。手間をかけずに支出を自動で記録・分類できる点が大きな魅力です。
レシートをスマートフォンで撮影するだけで品目や金額を読み取ったり、クレジットカードや銀行口座を登録しておけば利用履歴が自動で反映されたりするため、記録漏れや計算ミスを防ぐことが可能。
また、円グラフや棒グラフで支出の内訳を視覚的に確認できるため、どの費目に使いすぎているかが一目瞭然です。
日本国内で人気の家計簿アプリには、それぞれ特徴があります。自身のライフスタイルに合ったものを選ぶと良いでしょう。
| アプリ名 | 主な特徴 | 料金プラン |
|---|---|---|
| マネーフォワード ME | 連携できる金融機関・サービス数が非常に多い。資産全体の一元管理にも向いている。 | 無料版あり プレミアムサービス(月額制) |
| Zaim | レシートの自動読み取り精度が高いと評判。操作がシンプルで初心者でも使いやすい。 | 無料版あり プレミアムサービス(月額制) |
| OsidOri | 夫婦やカップルでの家計共有機能に特化している。共有口座と個人のお金を分けて管理できる。 | 無料 |
キャッシュレス決済で支出を一本化する
支出把握を容易にするためには、日々の支払いをクレジットカード決済にまとめることが有効な手段です。また、QRコード決済、電子マネーなどのキャッシュレス決済でも良いでしょう。
現金での支払いは記録が残りにくく、「何に使ったか分からないお金(使途不明金)」を生み出す大きな原因になります。一方、クレジットカードや電子決済は、全ての利用履歴がデータとして自動的に記録される点が大きな魅力。これらの明細は家計簿アプリと連携させることで、入力の手間を省くことができるでしょう。
メインで利用するクレジットカードを1枚に絞ったり、電子決済を特定のサービスに統一したりすることで、支出の管理がよりシンプルに。ポイント還元などの恩恵も受けやすくなるが、まずは支出を正確に把握するという目的意識を持って取り組むことが重要だ。
毎月の出費を抑える効果的な10の方法【固定費編】
固定費とは、住居費や通信費、保険料など毎月一定額がかかる支出のこと。
固定費の節約は、一度見直すだけで継続的な効果が期待できるため、出費を抑える上で最も優先度が高い項目です。
ここでは、効果が大きく、すぐに着手できる4つの固定費削減のコツを紹介します。
コツ①:通信費は格安SIMへの乗り換えで大幅に抑える
毎月のスマートフォン利用料金は、多くの家庭で大きな負担となっています。大手キャリア(NTTドコモ、au、ソフトバンク)を利用している場合、格安SIMやオンライン専用プランへ乗り換えることで、通信費を月々数千円、年間で数万円単位で削減できる可能性があります。
格安SIMは、大手キャリアの通信網を借りてサービスを提供しているため、通信品質は安定していることが多いです。まずは自身の毎月のデータ使用量を確認し、最適なプランを提供している会社を探すことから始めると良いでしょう。
| サービス種別 | サービス名 | 料金目安(データ容量20GB前後) |
|---|---|---|
| 大手キャリア | NTTドコモ、au、ソフトバンク | 約7,000円~ |
| オンライン専用プラン | ahamo, povo, LINEMO | 約3,000円 |
| 格安SIM(MVNO) | 楽天モバイル, UQモバイル, Y!mobileなど | 約2,000円~3,000円 |
※上記はあくまで目安であり、実際の料金は各社のプランやキャンペーンによって異なります。
コツ②:使っていないサブスサービスを減らす
動画配信、音楽配信、電子書籍、ソフトウェアなど、月額課金制のサブスクリプションサービスは非常に便利ですが、知らず知らずのうちに数が増え、家計を圧迫する原因になりがちです。
利用頻度が低い、あるいは全く使っていないサービスは、ためらわずに減らすことを検討しましょう。
まずはクレジットカードの明細やスマートフォンの契約状況を確認し、現在契約しているサービスをすべてリストアップすることから始めると良いでしょう。

「いつか使うかも」というサービスも、本当に必要になった時に再契約すれば良いと割り切ることが大切です。
コツ③:生命保険や自動車保険の内容を見直す
保険は万が一の備えとして重要ですが、ライフステージの変化によって必要な保障内容は変わります。
例えば、就職や結婚、出産、住宅購入といったタイミングで加入した保険を、そのままにしているケースは少なくないでしょう。
現在の自分の状況に合わない過剰な保障や特約を見直すことで、保険料を大幅に削減できる場合があります。
特に自動車保険は、運転者の範囲や年齢条件、車両保険の有無などを変更するだけで保険料が変わります。
複数の保険会社から見積もりを取り、保障内容と保険料のバランスが最適なプランを選ぶことが賢明です。
保険代理店の無料相談や、インターネットの一括見積もりサイトを活用するのも有効な手段でしょう。
コツ④:電力会社やガス会社のプランを比較検討する
2016年の電力自由化、2017年の都市ガス自由化により、私たちはライフスタイルに合わせて電力会社やガス会社を自由に選べるようになりました。しかし、依然として従来の電力・ガス会社と契約を続けている家庭も多いでしょう。
新電力や新ガス会社の中には、時間帯によって料金が安くなるプランや、ガスと電気のセット契約で割引が適用されるプランなど、多様な選択肢があります。
まずは検針票を用意し、インターネットの比較サイトで料金シミュレーションをしてみることをおすすめします。
毎月の出費を抑える具体的な10のコツ【変動費編】
変動費は、固定費とは異なり毎月の支払額が変動する支出のこと。代表的なものに食費、日用品費、交際費、娯楽費などがあり、日々の行動や意識次第でコントロールしやすいのが特徴です。
ここでは、今日から実践できる変動費の節約術を6つ紹介します。
コツ⑤:食費は自炊中心で賢く抑える
家計の支出の中でも大きな割合を占めるのが食費です。外食や中食(惣菜や弁当の購入)は手軽ですが、回数が増えればそれだけ出費もかさみます。
食費を効果的に抑える基本は、可能な範囲で自炊を心がけることです。無理のない範囲で自炊を取り入れるための、具体的な2つのアクションを紹介します。
週に一度のまとめ買いを習慣にする
スーパーへ行く回数が増えるほど、特売品や新商品など、予定外のものを買ってしまう「ついで買い」のリスクが高まります。
これを防ぐために、買い物は週に一度と決め、まとめ買いを習慣化するのが有効。事前に1週間のおおまかな献立を考え、必要な食材リストを作成してから買い物に行けば、無駄な出費を大幅に減らすことができるでしょう。
コンビニではなくスーパーを利用する
同じ商品でも、コンビニとスーパーでは価格が異なる場合が多いです。急な買い物や少量の買い物はコンビニが便利ですが、日常的な食料品や飲料の購入はスーパーマーケットを利用するのが節約の鉄則です。
特売日や夕方の見切り品タイムを狙うことで、さらに食費を圧縮できるでしょう。
コツ⑥:ポイ活とキャッシュレス決済を徹底活用する
日々の支払いを現金からキャッシュレス決済に切り替えるだけで、ポイントが貯まり、実質的な節約につながります。
PayPayや楽天ペイなどのQRコード決済、楽天カードやdカードなどのクレジットカードは、利用額に応じて0.5%〜1.0%以上のポイントが還元。
貯まったポイントは、次回の支払いに充当したり、特定の商品と交換したりできるため、現金で支払うよりも確実にお得です。
特定の店舗で還元率がアップするキャンペーンなどを活用し、効率的にポイントを貯める「ポイ活」を意識しましょう。
コツ⑦:飲み物はマイボトルを持参して出費をカット
外出先で何気なく購入するペットボトル飲料も、積み重なれば大きな出費となります。
例えば、1本150円の飲み物を平日に毎日購入した場合、1ヶ月で約3,000円、年間では36,000円もの出費に。
自宅で沸かしたお茶や水を入れたマイボトル(水筒)を持参するだけで、この出費をほぼゼロにできます。
毎日の小さな習慣が、年間で見れば数万円位の節約を生み出すことを意識しよう。
| 期間 | 支出額の目安(1日1本150円で購入した場合) |
|---|---|
| 1ヶ月(20日間) | 3,000円 |
| 6ヶ月(120日間) | 18,000円 |
| 1年間(240日間) | 36,000円 |
コツ⑧:日用品はプライベートブランドを選ぶ
ティッシュペーパーや洗剤、掃除用品などの日用品は、メーカー品(ナショナルブランド)ではなく、スーパーやドラッグストアが独自に開発・販売しているプライベートブランド(PB)商品を選ぶことで費用を抑えられます。
PB商品は、広告宣伝費や流通コストを削減しているため、同等の品質の商品を低価格で提供可能。
イオンの「トップバリュ」やセブン&アイ・ホールディングスの「セブンプレミアム」など、品質にこだわったPB商品も増えているため、積極的に活用しましょう。
コツ⑨:なんとなくの飲み会や外食への出費を見直す
人付き合いで断りきれず参加する飲み会や、作るのが面倒だからという理由での外食は、交際費や食費を圧迫する大きな要因です。
すべての誘いを断つ必要はありませんが、「なんとなく」の付き合いでの出費は見直しの対象としたいところ。
「月に2回まで」と上限を決めたり、「本当に会いたい人との食事に限定する」など、自分なりのルールを設けることが重要。
参加する場合でも、クーポンが利用できるお店を選ぶなど、少しの工夫で出費は抑えられます。
コツ⑩:図書館やフリマアプリを有効活用する
読書や映画鑑賞などの娯楽費、新しい服や雑貨の購入費も、工夫次第で節約が可能です。まず、地域の図書館は最大限に活用したいところ。
書籍や雑誌はもちろん、CDやDVDも無料で借りることができるため、エンタメ費を大幅に削減できます。
また、洋服や家具、本などを購入する際は、まずメルカリやラクマといったフリマアプリで探す習慣をつけるとよいでしょう。
新品同様のものが格安で手に入る可能性があるほか、自身の不要品を売ることで収入を得ることも可能。
「買う」以外の選択肢を持つことが、賢い節約につながるでしょう。
出費を抑える生活を無理なく続けるための3つの秘訣
出費を抑える生活は、一度や二度成功しても意味がありません。大切なのは、それを無理なく「続ける」こと。しかし、切り詰めるだけの節約はストレスが溜まり、長続きしないものです。
ここでは、節約を挫折させず、楽しみながら継続するための3つの秘訣を紹介します。
具体的な節約目標を立てる
「なぜ出費を抑えるのか」という目的が曖昧なままでは、節約へのモチベーションは維持しにくいでしょう。
「なんとなく貯金したい」ではなく、具体的でワクワクするような目標を設定することが、継続の第一歩です。
目標が明確であれば、日々の小さな節約も大きな目的に繋がっていると実感でき、やりがいが生まれるでしょう。
目標設定の際は、以下の表のように「目的」「目標金額」「期間」を具体的に定めるのがおすすめです。
| 目的の例 | 目標金額 | 期間 | 月々の節約目標額 |
|---|---|---|---|
| 1年後に沖縄旅行へ行く | 12万円 | 1年間 | 1万円 |
| 半年後に高性能なパソコンを買い替える | 15万円 | 6ヶ月 | 2.5万円 |
| 2年後の引っ越し費用に充てる | 36万円 | 2年間 | 1.5万円 |
このように具体的な数値を設定することで、日々の行動計画も立てやすくなります。
完璧を目指さずゲーム感覚で楽しむ
節約生活において、完璧主義は最大の敵である。「今月は少し使いすぎてしまった」というだけで自己嫌悪に陥り、すべてを投げ出してしまうケースは少なくありません。
大切なのは、100点満点を目指すのではなく、70〜80点の出来でも自分を許し、継続することです。
節約を「我慢」ではなく「ゲーム」と捉え直してみると良いでしょう。例えば、以下のような考え方が有効です。
- 毎月の予算を「クリアすべきクエスト」と考える。
- 節約できた金額を「経験値」として家計簿アプリに記録し、レベルアップを楽しむ。
- 固定費を削減できたら「強力な装備を手に入れた」と考える。
このように、少し視点を変えるだけで、日々の節約は義務から楽しみへと変わります。少しの失敗は気にせず、来月からまた挑戦すれば良いのです。
節約できたら自分にご褒美をあげる
継続のためには、適度な「アメ」も必要不可欠です。
目標を達成したり、一定額の節約ができたりした際には、自分自身にささやかなご褒美を用意しましょう。
これにより、節約のモチベーションがさらに高まり、ポジティブなサイクルが生まれます。
ただし、ご褒美が家計を圧迫してしまっては本末転倒。
「節約できた金額の10%をご褒美予算にする」など、あらかじめルールを決めておくのが賢明です。
ご褒美の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 普段は行かない少しリッチなカフェで過ごす
- 読みたかった本や漫画を1冊買う
- 好きな入浴剤を入れてゆっくりお風呂に入る
- コンビニの新作スイーツを食べる
頑張った自分をきちんと褒めてあげることで、次の節約への活力が湧いてくるでしょう。
まとめ
本記事では、毎月の出費を抑えるための具体的な10のコツを固定費と変動費に分けて解説しました。
節約を成功させる鍵は、まず家計簿アプリなどで現状の支出を正確に把握すること。その上で、格安SIMへの乗り換えといった一度の見直しで効果が持続する「固定費」の削減。そして、自炊やポイ活など日々の小さな積み重ねが重要な「変動費」の削減を両立させることが大切です。
完璧を目指さず、具体的な目標を立てて楽しみながら実践することが、無理なく続ける秘訣。また、出費の管理は将来の安心につながります。
まずは一つでも取り組めそうなことから始めてみましょう。