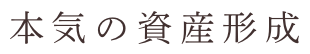「そろそろ、がん保険を見直したほうが良いかな?」
こう考えている方も多くいるでしょう。
私はFPという職業柄、保険についてもよく聞かれるので、
「がん保険の見直しを考えるべき絶好のタイミング」と、
「保障内容を確認する際の重要ポイント」を
具体的に解説していきます。
- 加入してからしばらく、がん保険を見直していない人
- 結婚や子育てなどライフステージに大きな変化があった人

この記事では、がん保険で損をしない見直しのタイミングとポイントを解説。
さらに、見落としがちなデメリットについても触れています。
私が実際に保険を見直す際に意識している点をまとめています。
できるだけ分かりやすく説明するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
なぜ今がん保険の見直しが必要なのか
「一度がん保険に入ったから、もう安心!」と考えていませんか?しかし、医療は日々進歩しており、がん治療の方法も大きく変化しています。以前は十分だった保障内容が、現在の医療事情に合わなくなっている可能性も。まずは、なぜ今がん保険の見直しが重要なのか、その理由から見ていきましょう。
がん治療の最新事情 通院治療の増加と高額な治療費
かつて、がん治療といえば長期入院が当たり前でした。しかし、医療技術の進歩により、現在では身体への負担が少ない手術や、副作用を抑えた抗がん剤治療などが登場。がん治療による入院日数は短期化する傾向にあります。
厚生労働省の調査でも、入院せずに外来で治療を受ける患者数が増加していることが示されています。
その結果、主流は「通院」による治療へとシフトしています。しかし、通院治療であっても、治療費が安くなるわけではありません。
分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬といった新しい薬は効果が期待できる一方で、非常に高額になるケースがあります。また、公的医療保険が適用されない先進医療や自由診療を選択した場合、数百万円以上の自己負担が発生することもあります。
治療の選択肢が広がった分、経済的な備えの重要性はますます高まっているのです。
古いタイプのがん保険では対応できないケース
がん治療の最新事情を踏まえると、古いタイプのがん保険では保障が不十分な可能性があります。具体的には、次のようなケースが考えられます。
一つ目は、「入院給付金」が保障の中心となっている場合です。前述の通り、現在は通院治療が主流のため、入院日数が短くなっています。そのため、入院日数に応じて支払われる給付金だけでは、高額な通院治療費をカバーしきれないかもしれません。また、通院保障が付いていたとしても、「入院後の通院」のみが対象など、条件が限定的な場合もあります。
二つ目は、診断給付金(診断一時金)の保障範囲や給付条件です。例えば、ごく初期のがんである「上皮内新生物」が保障の対象外であったり、給付額が大幅に減額されたりする保険があります。また、がんの再発・転移に備えるうえで重要な「複数回給付」の条件が厳しく設定されているケースも見られます。
このように、加入しているがん保険が現在の医療実態に合っていないと、いざという時に「思ったような給付金が受け取れない」という事態に陥りかねません。だからこそ、定期的な保障内容の確認と見直しが必要不可欠なのです。
がん保険を見直す絶好のタイミング5選
がん保険は一度加入したら終わりではありません。ご自身の状況や医療環境の変化に合わせて、保障内容を最適化することが重要です。ここでは、がん保険の見直しを検討すべき代表的な5つのタイミングについて具体的に解説します。
保険の更新時期が来たとき
保険期間が10年や15年で設定されている「定期型」のがん保険に加入している場合、更新のタイミングは見直しの絶好の機会です。
更新型の保険は、更新時の年齢で保険料が再計算されるため、一般的に保険料が上がります。保障内容は変わらないのに、月々の負担だけが増えてしまうことも少なくありません。
更新のお知らせが届いたら、そのまま継続するのではなく、現在の医療事情に合った他の保険商品と比較検討してみましょう。
より手厚い保障をより安い保険料で得られる可能性や、一生涯保障が続く「終身型」への切り替えも視野に入れることをおすすめします。
結婚や出産など家族構成が変わったとき
結婚や出産、子どもの独立など、ライフステージに大きな変化があったときも、保険を見直す重要なタイミングです。
独身時代に加入したがん保険は、自分一人の治療費をカバーする目的だったかもしれません。しかし、家族が増えれば、万が一の際に配偶者や子どもの生活を守るという視点が必要になります。
例えば、がんの治療で働けなくなった場合の収入減少を補う給付金や、家族のための生活費を考慮した保障額に見直すことで、より安心して治療に専念できる環境を整えることができます。
住宅ローンを組んだとき
住宅ローンを組む際に加入する「団体信用生命保険(団信)」の内容は、がん保険の見直しを考える上で非常に重要です。近年、がんと診断されただけで住宅ローンの残高がゼロになる「がん保障特約付き団信」が主流になっています。もし、この特約付きの団信に加入した場合、これまで住居費のために備えていたがん保険の保障が過剰になる可能性があります。団信の保障内容をしっかり確認し、がん保険と保障が重複している部分があれば、その分を削減して保険料を抑え、診断給付金や治療給付金など、団信ではカバーできない部分を手厚くするといった最適化を図りましょう。
40代や50代など節目の年齢になったとき
がんの罹患率は、年齢とともに上昇する傾向にあり、特に40代後半から50代にかけてリスクが急増します。そのため、40代や50代といった節目の年齢は、がんへの備えを本格的に見直すべきタイミングと言えます。若い頃に加入した保険のままだと、現在の自分のリスクに見合った保障額ではなかったり、最新の治療法に対応していなかったりする場合があります。体力や収入に比較的余裕があり、健康状態も良好なうちに、将来のリスクに備えて保障内容を点検し、必要であればより充実した内容の保険へ切り替えることを検討しましょう。
新しい保障内容のがん保険が登場したとき
がん治療の技術は日進月歩で進化しており、それに伴ってがん保険の商品内容も変化しています。かつては入院が治療の中心でしたが、現在では通院による抗がん剤治療、放射線治療、ホルモン剤治療が主流です。また、「先進医療」や、公的保険適用外の「自由診療」など、高額になりがちな治療の選択肢も増えています。ご自身が加入している保険が、こうした最新の治療法に対応できているか確認することが大切です。新しい治療に対応した通院保障や、先進医療特約などが付いた新しい保険商品が登場した際は、自分の保険と比較し、見直しを検討する良い機会です。
失敗しないがん保険見直しのチェックポイント7つ
がん保険の見直しで後悔しないためには、現在の保障内容と新しい保険の保障内容を正しく比較することが不可欠です。ここでは、特に重要となる7つのチェックポイントを解説します。ご自身の保険証券と見比べながら確認してみてください。
診断給付金の保障範囲と給付回数
がんと診断されたときにまとまった一時金を受け取れる「診断給付金(診断一時金)」は、がん保険の核となる保障です。治療費だけでなく、当面の生活費にも充てられるため、使い道の自由度が高いのが特徴です。この診断給付金については、保障されるがんの種類と、受け取れる回数を必ず確認しましょう。
上皮内新生物は保障されるか
「上皮内新生物(上皮内がん)」は、がん細胞が臓器の表面にとどまっている初期のがんです。古いタイプのがん保険では、この上皮内新生物が保障の対象外であったり、給付金が通常のがん(悪性新生物)の10%や50%など、減額して支払われたりする場合があります。見直しの際には、上皮内新生物でも満額の給付金が支払われるかを確認することが重要です。
複数回給付の条件を確認
がんは再発や転移のリスクがある病気です。そのため、2回目以降のがんにも備えられる複数回給付タイプの診断給付金が主流になっています。ただし、「前回の給付から1年以上または2年以上経過していること」「入院を伴う治療が条件」など、保険会社によって支払いの条件は様々です。どのような条件で複数回の給付が受けられるのか、その詳細をしっかり確認しましょう。
入院給付金の支払い日数に制限はないか
かつてのがん治療は長期入院が一般的でしたが、医療の進歩により入院日数は短期化する傾向にあります。しかし、治療内容や経過によっては、再入院や長期の入院が必要になるケースも依然として存在します。古い保険では、1回の入院における支払い日数が「60日まで」「120日まで」といった上限が設けられていることが多くあります。がん治療に特化した保険を選ぶなら、入院日数の制限がない「支払い日数無制限」のタイプが安心です。
通院保障は充実しているか
現在のがん治療は、手術後の放射線治療や抗がん剤治療など、通院で行われるケースが非常に増えています。そのため、入院だけでなく通院治療もしっかりと保障されるかが重要なポイントです。「入院後の通院のみ保障」といった条件付きではなく、入院を伴わない通院治療でも給付金が支払われるか、また、保障される日数や上限金額は十分かを確認しましょう。
先進医療特約は付いているか
先進医療とは、公的医療保険の対象外となる先進的な医療技術のことで、その技術料は全額自己負担となり、数百万円に及ぶこともあります。代表的なものに「陽子線治療」や「重粒子線治療」があります。この高額な技術料を保障するのが「先進医療特約」です。いざという時に治療の選択肢を狭めないためにも、この特約が付いているか、また保障額が十分か(通算2,000万円が一般的)を確認しておきましょう。
抗がん剤や放射線治療の保障内容
診断給付金とは別に、三大治療(手術・放射線治療・抗がん剤治療)を受けた際に給付金が支払われる保障も重要です。特に、通院治療の柱となる抗がん剤治療(ホルモン剤治療なども含む)や放射線治療は、長期間にわたることがあります。治療を受けた月ごとに一定額が支払われる「治療給付金」のような保障があると、長期化する治療の経済的負担を大きく軽減できます。
保険料払込免除特約の条件
「保険料払込免除特約」は、がんと診断された場合に、それ以降の保険料の支払いが免除される特約です。闘病中は収入が減少する可能性もあり、この特約は経済的にも精神的にも大きな支えとなります。見直しの際は、この特約が付加できるかを確認しましょう。また、免除となる条件が「悪性新生物」と診断された場合のみか、「上皮内新生物」でも適用されるのか、という点も重要な比較ポイントです。
保障期間は終身か定期か
がん保険には、保障が一生涯続く「終身タイプ」と、10年ごとなどで更新が必要な「定期タイプ」があります。がんは年齢とともに罹患率が高まる病気のため、保障が途中で途切れることなく、加入時の保険料のまま一生涯続く「終身タイプ」が基本となります。定期タイプは加入時の保険料は割安ですが、更新のたびに保険料が上がり、最終的に保障が終了してしまいます。見直しの際には、終身保障を基本に検討することをおすすめします。
がん保険見直しのデメリットと注意点
がん保険の見直しは、保障内容を時代に合わせて最適化できるメリットがある一方、いくつかのデメリットや注意点も存在します。メリットだけに目を向けて安易に見直しを進めると、かえって保障が手薄になったり、保険料の負担が増えたりする可能性があります。ここでは、見直しを検討する際に必ず押さえておきたい4つのポイントを解説します。
年齢が上がると保険料が高くなる
がん保険をはじめとする生命保険は、加入時の年齢が高いほど病気になるリスクが上昇するため、保険料も高く設定されるのが一般的です。現在加入している保険を解約し、新しい保険に入り直す場合、加入時の年齢は「見直しをする時点の年齢」になります。そのため、たとえ保障内容が同じでも、以前加入したときより年齢が上がっている分、月々の保険料が割高になるケースが多くあります。
健康状態によっては加入できない可能性がある
新しいがん保険に加入する際には、現在の健康状態や過去の病歴などを保険会社に正しく申告する「告知義務」があります。健康診断で異常を指摘されたり、持病の治療中であったり、過去に大きな病気を経験していたりすると、健康状態によっては新しい保険に加入できない可能性があります。また、加入はできても「特定の部位は保障しません」といった特別な条件が付くこともあります。現在の保険を解約した後に、新しい保険に加入できなかった場合、がんに対する備えが全くない「無保険」の状態になってしまうリスクがあるため注意が必要です。
保障がなくなる空白期間が生じるリスク
保険の見直しは手順が非常に重要です。もし、現在加入している保険を解約してから新しい保険の申し込み手続きを始めると、新しい保険の契約が成立するまでの間、保障が一切ない「空白期間」が生まれてしまいます。この空白期間中に万が一がんと診断されても、古い保険は解約済み、新しい保険は未成立のため、どちらからも給付金を受け取ることができません。見直しを行う際は、必ず「新しい保険の契約が成立し、保障が開始されたことを確認してから、古い保険を解約する」という手順を徹底しましょう。
新しい保険の免責期間に注意
がん保険には、一般的に「免責期間」が設けられています。これは、契約が成立してから90日間(約3ヶ月)など、保険会社が定める一定期間内にがんと診断されても、給付金が支払われないという決まりです。保険を見直して新しいがん保険に加入すると、この免責期間が新たにスタートします。古い保険を解約するタイミングと、この免責期間を考慮しないと、保障の空白期間はなくても、実質的にがんの保障が受けられない期間が発生してしまうため、十分に注意が必要です。
がん保険の見直しをスムーズに進める3ステップ
がん保険の見直しは、やみくもに進めると時間も手間もかかってしまいます。ここでは、現在の保険内容の確認から新しい保険の契約まで、失敗なくスムーズに進めるための具体的な3つのステップを解説します。
ステップ1 現在の保険の保障内容を把握する
見直しの第一歩は、現在加入しているがん保険の保障内容を正確に把握することです。「保険証券」や「ご契約のしおり・約款」を手元に用意し、どのような場合に、いくら給付金が支払われるのかを確認しましょう。特に、診断給付金の支払条件、入院・通院給付金の日額や日数、先進医療特約の有無といった、この記事で解説したチェックポイントを中心に確認することが重要です。もし書類が見当たらない場合は、契約している保険会社のウェブサイトやコールセンターで確認できます。
ステップ2 新しい保険に求める条件を整理する
現在の保障内容を把握したら、次に自分や家族にとって「どのような保障が必要か」を具体的に考え、優先順位をつけます。例えば、「最新の治療に対応できるよう、通院保障を手厚くしたい」「がんと診断された時点でまとまった一時金が欲しい」「保険料は月々〇〇円以内に抑えたい」など、希望する条件を書き出してみましょう。家族構成やライフプラン、家計の状況を考慮しながら、新しい保険に求める条件を明確にすることが、最適な保険選びにつながります。
ステップ3 複数の保険商品を比較検討し専門家に相談する
求める条件が固まったら、一つの保険会社に絞らず、複数の保険会社の商品を比較検討しましょう。保障内容や保険料は会社によって大きく異なるため、比較することでより自分に合った保険を見つけやすくなります。保険会社のウェブサイトや比較サイトを活用するのも良い方法です。また、保険の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)や保険代理店の担当者に相談することも有効です。客観的な視点からアドバイスをもらうことで、自分では気づかなかった点や、より良い選択肢が見つかる可能性があります。最終的には専門家のアドバイスも参考にしつつ、ステップ2で整理した条件と照らし合わせ、納得できる保険を選びましょう。
まとめ
がん保険の見直しは、変化するがん治療の実態に保障を合わせるために非常に重要です。医療技術の進歩により、通院治療の増加や高額な治療法が登場し、古い保険では保障が不十分になる可能性があるためです。保険の更新やライフステージの変化といったタイミングで、診断給付金の範囲や通院保障などを確認しましょう。見直しには保険料が上がるといったデメリットもありますが、まずは現在の保障内容を把握し、本記事で解説したポイントを参考に、ご自身に最適な保険を検討することをおすすめします。