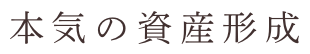本ページはプロモーションが含まれます。
「いま話題の新NISAを始めてみようかな!」
こう考えている方も多くいるでしょう。
投資歴10年のFPという職業柄、資産運用についてもよく聞かれるので、
「新NISAと旧NISAの違い」と、
「新NISAの仕組み」を
具体的に解説していきます。
- 雑誌やYoutubeで話題の新NISAが気になっている人
- 新NISAは従来の制度からどう変わったのか知りたい人

この記事では、投資歴10年のFPが、新・旧NISAの違いについて解説します。
私が実際に保険を見直す際に意識している点をまとめています。
できるだけ分かりやすく説明するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
新NISAと旧NISAの基本概要
少額投資非課税制度(NISA)は、家計の現預金を長期・積立・分散投資へ促し、配当金や譲渡益を非課税にすることで、日本の個人資産形成を後押しする制度だ。2024年からは制度改正で「新NISA」が始まり、従来の一般NISA・つみたてNISA(以下、旧NISA)と併存せず完全移行する。
NISA制度の目的と仕組み
NISA制度の目的は、「投資を通じた自助努力による資産形成の支援」と「市場への資金循環」を同時に達成することだ。国は利子非課税制度(マル優)に代わる新たな税制優遇として2014年に一般NISAを導入し、2018年には長期積立特化のつみたてNISAを追加した。
旧NISA(一般NISA・つみたてNISA)のデメリット
2023年まで運用されていた旧NISAですが、以下のようなデメリットがありました。
- 非課税期間が有限で、終了後は課税口座へ移管するか課税される。
- 年間投資枠が小さく、一括投資・高配当株投資の機会が限られる。
- 売却しても非課税枠が翌年復活しないため、機動的なリバランスが難しい。
- ロールオーバー手続きや管理が煩雑で、運用コスト増につながる。
2024年スタート!新NISAのメリットとは
非課税期間が無期限化され、枠が復活するため、投資家は長期保有と売却・再投資を自由に選択できる。
- 年間360万円、総額1,800万円までの大幅な非課税拡大で資産形成の自由度が向上。
- 成長投資枠と積立投資枠を同一年に併用でき、多様な投資スタイルに対応。
- 制度恒久化により、ライフプランに合わせた長期・中期・短期の組み合わせが可能。
- 売却済み額が非課税枠へ再利用されるため、ポートフォリオ管理が容易。
以上が新旧NISAの基本的な仕組みと特徴だ。以降では数値面の違いを具体的に比較していく。
新NISAと旧NISA違いを徹底比較
| 項目 | 新NISA(2024年~) | 旧NISA(~2023年) | ||
|---|---|---|---|---|
| 利用方法 | 併用可能 | 選択制 | ||
| 口座区分 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | つみたてNISA | 一般NISA |
| 年間非課税投資枠 | 120万円 | 240万円 | 40万円 | 120万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 20年間 | 5年間 | |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円 | 800万円 | 600万円 | |
| 1,200万円 | ||||
| 投資枠の復活 | 売却後、翌年以降に再利用可 | 不可 | ||
違い①:成長投資枠と積立投資枠の併用
1人あたり1口座で2つの投資スタイルを併用できるのが最大の特長。たとえば、毎月積立でインデックス投信を購入しつつ、余剰資金で高配当ETFをスポット買いするなど、資金計画に応じて柔軟に設計できる。
併用によるリスク分散効果
積立枠で時間分散、成長枠で銘柄分散を図ることで、景気サイクルに左右されにくいバランス運用が可能となる。
違い②:年間非課税投資枠の拡大
新NISAは、つみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円を併用することで、年間360万円まで非課税で投資できる点が大きな魅力だ。
従来のつみたてNISA40万円、一般NISA120万円と比べ、2倍以上の投資余力が生まれる。短期的な値上がり益を狙いたい株式と、長期積立に適した投資信託を併用しやすくなるため、ポートフォリオ構築の自由度が大幅に高まるだろう。
成長投資枠240万円
国内外株式・ETF・REITなど値動きの大きい商品を中心に投資可能。配当金や売却益が非課税になるため、高配当株投資との相性が良い。
積立投資枠120万円
つみたてNISA同様、金融庁が選定した長期積立向け投資信託が対象。ドルコスト平均法でリスクを抑えながら運用できる。
違い③:非課税保有期間の撤廃
旧NISAでは一般5年、つみたて20年と上限が定められていたため、期間終了時にロールオーバーの手続きや課税口座への移管といった煩雑さがあった。新NISAは非課税期間が恒久化され、「長期保有=複利効果の最大化」が実現しやすい。
違い④:売却による非課税枠の復活
新NISAでは売却した翌年以降に同額の非課税枠が復活するため、キャッシュポジションの確保やポートフォリオの入れ替えがしやすい。旧NISAでは一度使った枠は消滅し、再利用できなかった点が大きく改善された。
活用例
大幅に値上がりした個別株を売却し、確定した利益を翌年の枠でインデックス投信に振り向けるなど、相場状況に応じて機動的に資産配分を調整できる。
新NISAと旧NISA違いをわかりやすく解説:まとめ
以上のことをまとめると、新NISA・旧NISA違いは以下のとおり。
| 項目 | 新NISA(2024年~) | 旧NISA(~2023年) | ||
|---|---|---|---|---|
| 利用方法 | 併用可能 | 選択制 | ||
| 口座区分 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | つみたてNISA | 一般NISA |
| 年間非課税投資枠 | 120万円 | 240万円 | 40万円 | 120万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 20年間 | 5年間 | |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円 | 800万円 | 600万円 | |
| 1,200万円 | ||||
| 投資枠の復活 | 売却後、翌年以降に再利用可 | 不可 | ||
旧NISAは「少額・期間限定」の非課税制度だったが、新NISAは「生涯1,800万円・無期限・売却枠復活」と大幅に進化した。年間上限360万円の枠をフルに生かすため、早期に口座を開設しライフプランに合わせた戦略的投資を始めることが、長期的な資産形成成功のカギとなる。
よくある質問Q&A
非課税限度額を使い切れなかった場合は?
年間360万円の未使用枠は翌年に繰り越せず失効する。ただし売却によって翌年に同額が復活するため、長期で計画的に投資すれば生涯投資枠1,800万円をフル活用しやすい。
途中で新NISA口座の名義変更は可能?
死亡・贈与以外の理由で名義を途中変更する制度は存在しない。結婚などで姓が変わる場合は同一人物とみなされるため、証券会社に戸籍抄本などを提出して名義訂正を行う。
新NISAの運用はふるさと納税に影響する?
新NISAで得た非課税運用益は課税所得に含まれないため、ふるさと納税の控除上限額を左右しない。給与や事業所得など本来の課税所得を基準に上限額を計算すればよい。
現行NISA口座は新NISA口座に移行できる?
2024年以降、現行NISA口座を保有している投資家は自動で新NISA口座が開設される。旧制度で買い付けた商品は非課税期間終了まで現行ルールが適用され、ロールオーバーは最後の非課税期間終了時(一般NISAは2028年)まで可能。
金融機関切り替えの注意点・手続きは?
- 同一年内に複数の金融機関で買い付け不可。変更は年単位。
- 変更届出書を提出し、旧金融機関で口座廃止→新金融機関で口座開設。
- 保有商品の移管には移管手数料が発生する場合がある。
- 移管中は売却・買付が制限される期間が生じるため市場変動リスクに注意。
証券会社と銀行、口座開設するならどっちがおすすめ?
売買手数料・商品ラインナップ・取引ツールの観点でネット証券が優位。一方で対面サポート重視なら銀行や店舗型証券も選択肢となる。以下の観点で比較すると選びやすい。
| 比較項目 | ネット証券 | 銀行・店舗型証券 |
|---|---|---|
| 取扱商品 | 国内外株式・投資信託・ETFが豊富 | 投資信託中心で銘柄数は限定的 |
| 手数料 | 売買手数料無料~低水準 | 購入時手数料が高めのケースが多い |
| サポート | オンライン・チャット中心 | 対面相談・電話サポート |
| ポイント還元 | 決済ポイントやTポイント付与など | 独自の特典は限定的 |
低コストで幅広い商品を自分で選びたい人はネット証券、対面で相談したい初心者は銀行・店舗型証券を検討するとよい。