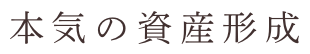本ページはプロモーションが含まれます。
「投資信託で初期投資として『100万』入れたらどうなる?」
こう考えている方もいるでしょう。
FPという職業柄、投資の考え方についてもよく聞かれるので、
「利回り別の具体的なシミュレーション方法」と、
「初期投資で『100万』入れた時の推移」を
広く一般的な視点で解説していきます。
- 投資信託の複利効果について知りたい人
- 将来に向けて資産形成を考えている人

この記事では、投資歴10年のFPが、投資信託の複利効果について解説。
初期投資『100万』を5年間運用した場合の資産額を利回り別にシミュレーション。
できるだけ分かりやすく説明するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
【結論】投資信託に初期投資100万円で5年後の資産額はこうなる
「もし投資信託に100万円を投資したら、5年後にはいくらになっているのだろう?」
多くの人が抱くこの疑問に、まず結論からお答えします。
利回り3% 5% 7%でのシミュレーション結果
投資信託の運用成果は、世界経済の成長と連動する傾向があります。
ここでは、現実的なリターンの目安として、以下3つのパターンで、100万円を一括投資した場合、5年間運用した場合の資産額を計算しました。
- 堅実な運用(年利3%)
- 平均的な運用(年利5%)
- 好調な運用(年利7%)
まずは税金や手数料を考慮しないシンプルな計算結果を見てみましょう。
| 年間利回り | 5年後の資産額 | 5年間の利益 |
|---|---|---|
| 3% | 約115.9万円 | 約15.9万円 |
| 5% | 約127.6万円 | 約27.6万円 |
| 7% | 約140.2万円 | 約40.2万円 |
年利5%で運用できた場合、100万円の元本が5年間で約127.6万円に増える計算になります。
銀行の普通預金金利(年0.001%程度)と比較すると、その差は歴然ですよね。
税金と信託報酬を考慮した現実的なシミュレーション
ただし、実際の資産運用では、投資信託を保有している間にかかる「信託報酬(手数料)」と、利益が出た時にかかる「税金」を考慮する必要がある。
より現実に即した手取り額を知るために、仮に信託報酬を年率0.1%、税率を20.315%として再計算してみよう。
| 年間利回り | 5年間の利益(税引前) | 税額(約20.315%) | 最終的な資産額(手取り) |
|---|---|---|---|
| 3% | 約15.3万円 | 約3.1万円 | 約112.2万円 |
| 5% | 約27.0万円 | 約5.5万円 | 約121.5万円 |
| 7% | 約39.6万円 | 約8.0万円 | 約131.6万円 |
手数料と税金を差し引いても、資産が着実に増える可能性が高いことがわかる。
結論として、初期投資100万円は5年後、年利5%で運用できた場合、現実的な手取り額で約121万円になるのが一つの目安と言えるだろう。
さらに、NISA(新NISA)の非課税制度を活用すれば、この利益にかかる税金(表の例では約5.5万円)が非課税となり、利益をそのまま受け取ることが可能。この制度を使わない手はない。
なぜ増える?投資信託100万円で資産形成を加速させる複利効果
投資信託で100万円を運用すると、なぜ資産が増えていくのだろうか。
その最大の理由は「複利効果」によるものだ。かの有名な物理学者アインシュタインが「人類最大の発明」と呼んだとも言われるこの効果は、資産形成を力強く後押ししてくれる。
複利とは、投資で得た利益(分配金など)を元本に加えて再び投資することで、その利益がさらに新たな利益を生み出す仕組みのこと。雪だるまが転がりながら雪を巻き込んでどんどん大きくなっていくように、資産が加速度的に増えていく効果が期待できる。
単利と複利ではこんなに違う!100万円の運用シミュレーション
複利のすごさを理解するために、元本に対してのみ利息がつく「単利」と比較してみよう。
初期投資100万円を年利5%で運用した場合、資産がどのように増えていくかを以下の表にまとめた。
| 経過年数 | 単利(年利5%)の場合 | 複利(年利5%)の場合 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 5年後 | 125万円 | 約128万円 | 約3万円 |
| 10年後 | 150万円 | 約163万円 | 約13万円 |
| 20年後 | 200万円 | 約265万円 | 約65万円 |
| 30年後 | 250万円 | 約432万円 | 約182万円 |
※税金や手数料は考慮しないものとする。
表を見ると一目瞭然だが、運用期間が長くなればなるほど、単利と複利の差は劇的に開いていく。これが、長期的な資産形成において複利が非常に重要である理由なのだ。
複利効果を最大化する2つのポイント
この強力な複利効果を最大限に活かすためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。
ポイント1:長期的な視点で運用する
先のシミュレーションで示した通り、複利効果は時間をかければかけるほど大きくなる。
投資を始めたばかりの頃は資産の増え方が緩やかに感じるかもしれないが、長期的に運用を続けることで、後半になるにつれて資産の増加ペースが加速していく。
短期的な価格の上下に一喜一憂せず、腰を据えて運用を続けることが成功の鍵だ。
ポイント2:「分配金再投資型」のファンドを選ぶ
投資信託には、運用で得た利益を「分配金」として投資家に支払うタイプがあるが、この分配金には「受取型」と「再投資型」の2種類が存在する。複利効果を狙うのであれば、分配金を受け取らずに自動で元本に組み入れて再投資してくれる「再投資型」を選択するべきだ。
複利の恩恵を最大限に受けるためには、分配金再投資型の投資信託を選ぶのが鉄則だと言える。
初期投資100万円は「一括投資」と「積立投資」どちらがおすすめか
まとまった資金100万円を投資信託で運用する場合、「一括投資」と「積立投資」という2つの方法が考えられる。一括投資は100万円を一度に投資する方法、積立投資は100万円を複数回に分けて定期的に投資する方法だ。
どちらにもメリットとデメリットがあり、どちらが最適かは投資家のリスク許容度や相場観によって異なる。ここでは両者の特徴を詳しく解説し、初心者にはどちらが向いているかを明らかにしよう。
一括投資のメリットとデメリット
一括投資は、手元にある100万円を一度にまとめて投資信託の購入に充てる方法を指す。相場が上昇局面にある場合、最も効率的に資産を増やせる可能性がある点が大きな魅力だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 相場が右肩上がりの場合、投資した全額が値上がり益の対象となるため、複利効果を最大限に活かせる。また、購入手続きが一度で済むため、手間がかからない点も大きな魅力。 |
| デメリット | 最大のデメリットは、購入した直後に相場が暴落した場合、大きな損失を被る「高値掴み」のリスクがあること。購入タイミングの見極めが非常に重要となり、精神的な負担も大きくなる傾向がある。 |
積立投資のメリットとデメリット
積立投資は、100万円を例えば「毎月5万円ずつ20ヶ月」のように、期間を分けて定期的に一定額を投資していく方法だ。購入タイミングを分散させる効果がある。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 定期的に一定額を購入することで、価格が高いときには少なく、安いときには多く購入する「ドルコスト平均法」の効果が得られます。これにより、平均購入単価を平準化でき、高値掴みのリスクを低減できます。精神的な負担が少なく、相場を常に気にする必要がないため、投資を続けやすいのが特徴です。 |
| デメリット | 購入タイミングが分散されるため、一貫して相場が上昇し続ける局面では、最初から全額を投資していた一括投資に比べてリターンが小さくなる可能性があります。また、投資が完了するまでに時間がかかります。 |
初心者にはどちらの投資方法が向いているか
結論から言うと、投資初心者の方には「積立投資」をおすすめする。
その最大の理由は、精神的な負担が少なく、長期的な資産形成を継続しやすい点にある。投資で最も避けるべきは、短期的な価格変動に一喜一憂し、恐怖心から損失が出ている状態で売却してしまう「狼狽売り」だ。
積立投資は購入タイミングを分散するため、一括投資に比べて価格変動による精神的ダメージを和らげる効果が期待でる。
投資において最も重要なのは「市場に居続けること」だ。その観点から、高値掴みのリスクを避け、心穏やかに続けられる積立投資は、初心者にとって最適な選択肢と言えるだろう。
もし、どうしても一括投資のメリットも享受したい場合は、「30万円を一括投資し、残りの70万円を毎月積立投資に回す」といったハイブリッドな方法も有効になる。
まずは自身が安心して続けられる方法で、資産形成の第一歩を踏み出すと良いだろう。
初期投資100万円で投資信託を始める具体的な4ステップ
投資信託を始めることは、決して難しいことではない。特にまとまった資金が100万円ある場合、スムーズにスタートを切ることができる。
ここでは、投資の知識が全くない初心者でも迷わないよう、具体的な4つのステップに分けて手順を解説する。
ステップ1 証券会社の口座を開設する
投資信託を購入するためには、まず金融機関の口座が必要だ。銀行の窓口でも購入できるが、手数料が安く、取扱商品が豊富なネット証券が圧倒的におすすめである。
口座開設はスマートフォンやパソコンからオンラインで完結し、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)と銀行口座があれば、申し込みから数日〜1週間程度で取引を開始できる。
おすすめはSBI証券か楽天証券
数あるネット証券の中でも、特に初心者におすすめなのがSBI証券と楽天証券だ。この2社は口座開設数がトップクラスで、多くの投資家から支持されている。
どちらを選ぶかは、普段利用しているポイントサービスや経済圏に合わせて決めるのが合理的といえる。
| 証券会社 | 特徴 | 相性の良いユーザー |
|---|---|---|
| SBI証券 | ネット証券口座開設数No.1。三井住友カードでのクレカ積立でVポイントが貯まるほか、Tポイント、Pontaポイント、dポイントなど複数のポイントサービスに対応している。 | 三井住友カードを持っている人や、様々なポイントサービスを使い分けたい人。 |
| 楽天証券 | 楽天グループの証券会社。楽天カードでのクレカ積立や楽天キャッシュ決済で楽天ポイントが貯まり、ポイントを使って投資信託を購入することも可能。楽天経済圏との連携が強み。 | 楽天市場や楽天カードなど、普段から楽天のサービスをよく利用する人。 |
ステップ2 お得なNISA制度を活用する
証券口座の開設と同時に、必ずNISA(ニーサ)口座も開設しよう。
NISAは「少額投資非課税制度」の愛称で、この制度を利用して得た投資の利益(分配金や売却益)には税金がかからないという非常に大きなメリットがある。通常、投資の利益には20.315%の税金がかかるため、この差は将来の資産額に大きく影響する。
2024年から始まった新NISAには、「つみたて投資枠(年間120万円)」と「成長投資枠(年間240万円)」の2つの枠がある。初期投資100万円であれば、成長投資枠を使って一括で購入したり、両方の枠を組み合わせて投資したりと、柔軟な活用が可能だ。
ステップ3 投資する投資信託を選ぶ
口座の準備が整ったら、次に100万円を投じる投資信託(ファンド)を選ぶ。投資信託は国内外に数千本以上存在するため、初心者はどれを選べば良いか迷ってしまうだろう。しかし、失敗しないための王道といえる選び方がある。
重要なポイントは、手数料(信託報酬)が低コストで、幅広い国や地域に分散投資できるインデックスファンドを選ぶことだ。具体的な選び方やおすすめの銘柄については、後の章で詳しく解説する。まずはこの基本方針を覚えておこう。
ステップ4 100万円で投資信託を購入する
投資する銘柄が決まれば、いよいよ最後の購入ステップだ。
証券会社のウェブサイトやアプリにログインし、購入したい投資信託の名前を検索する。購入画面に進み、「一括投資(金額指定)」を選択。投資金額に「購入する金額」を入力する。
このとき、必ずNISA口座(成長投資枠)を指定して購入することを忘れないようにしたい。課税口座(特定口座や一般口座)で購入してしまうと、非課税の恩恵を受けられないため、注意が必要だ。
注文内容や投資信託の説明書(目論見書)を最終確認し、取引パスワードなどを入力して発注すれば、手続きは完了する。これであなたも投資家の仲間入りだ。
100万円の初期投資で失敗しない投資信託の選び方
投資信託は日本国内だけでも6,000本以上存在し、初心者にとってはどれを選べば良いか迷ってしまうのが正直なところだろう。しかし、100万円という大切な資金を投じる上で、失敗の確率を減らすための選び方には明確な基準が存在する。
ここでは、長期的な資産形成を目指す上で押さえておきたい3つの重要なポイントを解説する。
手数料(信託報酬)が低いインデックスファンドを選ぶ
投資信託を保有している間、継続的に発生するのが「信託報酬」というコストだ。この手数料は運用資産から毎日差し引かれるため、たとえわずかな差でも長期間になるとリターンに大きな影響を及ぼす。
資産形成の成功確率を高めるには、この信託報酬を極力低く抑えることが鉄則である。
投資信託は運用方針によって、市場平均(インデックス)との連動を目指す「インデックスファンド」と、市場平均を上回るリターンを目指す「アクティブファンド」に大別される。
一般的に、アクティブファンドは調査や分析に手間がかかる分、信託報酬が高くなる傾向にある。しかし、長期的に見てインデックスファンドを上回る成績を出し続けるアクティブファンドはごく一部だ。
そのため、特に初心者の方は、低コストで市場全体の成長の恩恵を受けられるインデックスファンドを選ぶのが賢明な選択と言える。信託報酬の具体的な目安としては、年率0.2%以下であれば十分に低い水準と判断して良いだろう。
投資先は全世界株式か米国株式(S&P500)が王道
投資先の選択は、将来のリターンを大きく左右する重要な要素だ。数ある投資先の中でも、長期的な成長が期待でき、多くの投資家から支持されているのが「全世界株式」と「米国株式(S&P500)」である。
全世界株式は、その名の通り日本を含む先進国や新興国など、世界中の株式にまとめて投資するスタイルだ。世界経済全体の成長を原動力とするため、特定の国や地域が不調でも他の地域の成長でカバーできる、優れた分散効果が魅力である。
一方、米国株式(S&P500)は、AppleやMicrosoftといった世界を代表する米国の主要企業約500社に投資するスタイルだ。これまで世界経済を力強く牽引してきた実績があり、今後もイノベーションを創出し続けるであろう米国経済の成長に期待するなら有力な選択肢となる。
それぞれの特徴を下記にまとめる。
| 投資対象 | 特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| 全世界株式(オール・カントリー) | これ1本で世界中の国・地域の株式に分散投資できる。世界経済の成長を丸ごと享受できる。 | 究極の分散投資を手間なく実現したい人。どの国が成長するか予測するのは難しいと考える人。 |
| 米国株式(S&P500) | 世界経済を牽引する米国の主要企業約500社に集中投資。過去の実績が豊富で力強い成長が期待できる。 | 今後の世界経済も米国が中心となって成長していくと考える人。より高いリターンを期待したい人。 |
1つの銘柄で分散投資が実現できるものを選ぶ
「卵は一つのカゴに盛るな」という投資格言があるように、資産を一つの対象に集中させることは大きなリスクを伴う。投資信託の大きなメリットは、一つの商品を購入するだけで、自然と多数の銘柄に資産を分けて投資する「分散投資」が実現できる点にある。
特に、前述した「全世界株式」や「S&P500」に連動するインデックスファンドは、1本購入するだけで数百から数千の企業に自動的に分散投資してくれるため、非常に効率的だ。100万円の初期投資を複数のファンドに分けることも可能だが、まずは質の高いインデックスファンド1本に絞ることで、管理の手間を省きつつ、十分な分散効果を得ることができる。
初心者が複数の投資信託を組み合わせようとすると、結果的に投資先が重複してしまったり、管理が煩雑になったりするケースも少なくない。まずは王道のインデックスファンド1本から始め、投資に慣れてからポートフォリオの調整を検討するのがおすすめだ。
【厳選】初期投資100万円におすすめの投資信託3銘柄
ここでは、これまでの内容を踏まえ、初期投資100万円で始めるのに最適な、具体的かつ王道の投資信託を3つ厳選して紹介する。いずれも手数料が非常に低く、NISA制度の対象となっている銘柄だ。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
「オルカン」の愛称で親しまれている、投資初心者から上級者まで絶大な人気を誇るインデックスファンドだ。これ1本で日本を含む全世界の先進国・新興国の株式にまとめて分散投資できるため、「どの国に投資すれば良いか分からない」という方に最適解となる。
世界経済の成長をまるごと享受したいなら、まず検討すべき一本である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投資対象 | MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスに連動 |
| 特徴 | 全世界の約3,000銘柄に分散投資。世界経済全体の成長がリターンに繋がる。 |
| 信託報酬(年率・税込) | 0.05775% |
| NISA対応 | つみたて投資枠・成長投資枠の両方に対応 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
世界経済の中心である米国の主要企業約500社で構成される株価指数「S&P500」への連動を目指すインデックスファンドだ。AppleやMicrosoft、Amazonといった世界を代表する巨大テック企業にまとめて投資できるのが魅力。
近年の力強い米国経済の成長の恩恵をダイレクトに受けたいと考える方におすすめである。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投資対象 | S&P500指数に連動 |
| 特徴 | 米国の主要企業約500社に分散投資。世界経済を牽引する米国の成長に期待できる。 |
| 信託報酬(年率・税込) | 0.09372%以内 |
| NISA対応 | つみたて投資枠・成長投資枠の両方に対応 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と同様に、S&P500指数への連動を目指すファンドだが、最大の特徴はその信託報酬の低さにある。業界最安水準のコストで、米国株式市場に投資したいというコスト意識の高い投資家から絶大な支持を集めている。
長期運用において手数料の差はリターンに大きく影響するため、有力な選択肢となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投資対象 | S&P500指数に連動(主にバンガード社のETFを通じて投資) |
| 特徴 | S&P500に連動するファンドの中でも特に信託報酬が低い。 |
| 信託報酬(年率・税込) | 0.0938%程度 |
| NISA対応 | つみたて投資枠・成長投資枠の両方に対応 |
投資信託に100万円を投資する前に知っておくべき注意点とリスク
投資信託に100万円を投資することは、資産形成を加速させる大きな一歩である。しかし、期待と同時にリスクや注意点も正しく理解しておく必要がある。
ここでは、投資を始める前に必ず押さえておきたい3つの重要なポイントを解説する。
元本保証ではないことを理解する
最も重要な点は、投資信託は銀行の預貯金とは異なり、元本が保証されていない金融商品であるということだ。
投資信託の価格(基準価額)は、組み入れられている株式や債券などの市場価格の変動によって日々上下する。そのため、経済情勢や市場の動向によっては、購入時よりも基準価額が下落し、100万円の投資元本を下回る「元本割れ」のリスクが存在する。
このリスクを受け入れた上で、長期的な視点で資産の成長を目指すことが投資の基本となる。
短期的な価格変動に惑わされない
投資を始めると、日々の価格変動が気になってしまうかもしれない。特に100万円というまとまった金額を投資した場合、少しの値動きでも評価額が大きく変動するように感じられるだろう。
しかし、ここで重要なのは短期的な価格の上下に一喜一憂しないことだ。価格が下落した際に、恐怖心から焦って売却(狼狽売り)してしまうと、その後の価格回復の機会を逃し、損失を確定させてしまうことになりかねない。投資信託での資産形成は、数年単位の長期的な視点を持つことが成功の鍵である。
生活防衛資金は必ず確保しておく
投資は、あくまで「余裕資金」で行うのが大原則だ。余裕資金とは、当面の生活に必要なお金や、万が一の事態に備える「生活防衛資金」を差し引いた上で、長期的に使う予定のないお金のことである。
生活防衛資金が不足していると、予期せぬ病気や失業などで急にお金が必要になった際、価格が下落しているタイミングで投資信託を売却せざるを得ない状況に陥る可能性がある。
投資を始める前に、まずは十分な生活防衛資金を現金や預貯金で確保しておくことが極めて重要だ。
| あなたの状況 | 生活防衛資金の目安 |
|---|---|
| 会社員(独身) | 生活費の3ヶ月~6ヶ月分 |
| 会社員(家族あり) | 生活費の6ヶ月~1年分 |
| 自営業・フリーランス | 生活費の1年~2年分 |
今回投資を検討している100万円が、上記の生活防衛資金とは別の余裕資金であることを必ず確認しよう。
投資信託の初期投資100万円に関するよくある質問
ここでは、投資信託に100万円を初期投資する際によく寄せられる質問とその回答をまとめた。投資を始める前の不安や疑問を解消していこう。
100万円を複数の投資信託に分けても良いですか
結論から言うと、100万円を複数の投資信託に分けて投資することは可能であり、分散投資の観点からは有効な戦略の一つである。
しかし、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」のような全世界の株式に投資するインデックスファンドは、それ1本で世界中の数千社の株式に分散投資しているため、十分にリスク分散効果が期待できる。
初心者の場合、まずはこのようなバランスの取れた1本から始め、資産管理をシンプルにすることも賢明な選択だ。
もし複数のファンドに分けるのであれば、株式と債券、先進国と新興国など、異なる値動きをする資産クラスを組み合わせることで、よりポートフォリオ全体のリスクを低減させる効果が見込めるだろう。
もし購入後に暴落したらどうすればいいですか
購入後に市場が暴落した場合、最も重要なことはパニックにならず、冷静に行動することである。短期的な価格変動に一喜一憂し、慌てて売却してしまう「狼狽売り」は、損失を確定させてしまう最悪の選択肢となり得る。
投資信託での資産形成は、長期的な視点が不可欠だ。歴史的に見ても、株式市場は暴落を繰り返しながらも、長期的には右肩上がりに成長してきた。価格が下落した局面は、むしろ「優良な資産を安く買い増しできる絶好の機会」と捉えることもできる。
このような事態に冷静に対処するためにも、投資はあくまで余裕資金で行い、長期的な視点を持ち続けることを忘れないようにしたい。
5年後以降も運用を続けるべきですか
5年後という期間は、あくまで資産の成長をイメージするための一つの目安に過ぎない。もし、その時点で資金を使う明確な目的がないのであれば、複利効果を最大限に活かすためにも運用を続ける検討をしても良いだろう。
投資は運用期間が長ければ長いほど、複利の力が働き、資産が雪だるま式に増えていく効果が期待できる。また、長期で保有することで、短期的な価格変動のリスクを平準化させる効果もある。
ただし、「住宅購入の頭金にする」「子供の教育資金に充てる」といったライフイベントに合わせて資金が必要になった場合は、目標達成のために計画的に売却を検討する必要がある。
自身のライフプランと照らし合わせながら、柔軟に運用方針を判断していくことが重要だ。
まとめ
投資信託に初期投資100万円で運用した場合、5年後には複利効果で資産が増える可能性をシミュレーションで示した。
例えば年利5%なら、税金や信託報酬を考慮しても約128万円になる計算だ。この資産形成を成功させる鍵は、非課税メリットが大きいNISA制度を活用し、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」のような手数料の低いインデックスファンドを選ぶことにある。
初心者にはリスクを時間で分散できる積立投資が向いている。元本保証ではないため、生活防衛資金を確保したうえで、短期的な価格変動に惑わされず長期的な視点で取り組むことが重要だ。